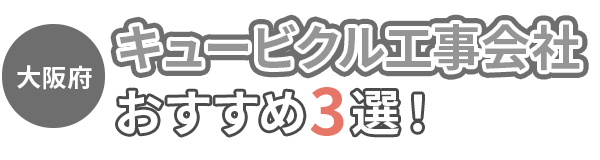キュービクルは、高圧電気を安全に利用するために欠かせない設備ですが、古い機器には有害物質のPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用されている場合があります。日本ではPCB特別措置法にもとづき、事業者が処分しなければなりません。この記事では、PCBの基礎知識から含有確認方法、さらに処分手順までをわかりやすく解説します。
PCBとは
キュービクルの工事や点検を考える際に、避けてとおれないのがPCBの問題です。PCBとは、ポリ塩化ビフェニル(Poly Chlorinated Biphenyl)の略称で、人工的に合成された油状の化学物質を指します。有害物質である
PCBが問題視される理由は、有害物質であるからです。PCBは脂肪に溶けやすく、体内に長期間にわたって蓄積してしまうと慢性的な中毒症状を引き起こす危険があります。実際に報告されている症状には、爪や口腔粘膜の色素沈着、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどがあります。こうしたリスクを背景として、1972年には日本国内で製造が中止され、2001年7月にはPCB特別措置法が施行されました。この法律は、PCBの紛失や漏えいによる環境汚染を防ぎ、安全に処理することを目的としています。
かつては広く普及していた
電気設備の分野では以前、PCBを含む機器が数多く存在していました。代表的なものとして、工場やビルに設置されていた変圧器やコンデンサー、さらに古い工場や学校の蛍光灯安定器などがあります。とくにキュービクル内に設置される変圧器にはPCBを含むものが多く、設備の老朽化にともない処理が必要となるケースが増えています。ただし、家庭用の蛍光灯にPCBが使用されたことはありません。つまり、リスクがあるのは主に事業所や公共施設、工場といった大規模な電気設備に限られるのです。
法律にもとづき処理する義務がある
PCBを含む機器は、PCB特別措置法のもと厳格に管理されており、事業者には保管や処理の状況を届け出る義務が課されています。また、保管しているだけでも適切な管理が求められ、万一漏えいや紛失があれば環境への影響は計り知れません。そのため、含有の有無を確認し、必要であれば専門業者に依頼して処理することが必須です。
PCB含有電気工作物とは?
キュービクルの更新や処分を検討する際に重要になるのが、PCB含有電気工作物という区分です。PCBを含む機器は、人体や環境に重大な影響をおよぼす可能性があるため、法律で厳格に管理されています。まず理解しておくべきは、PCBがどの程度含まれているかによって分類が変わるという点です。PCB含有電気工作物の基準
電気機器の中に含まれるPCB濃度が0.5mg/kg以上であれば、その機器はPCB含有電気工作物にあたります。PCB含有と認定された時点で、所有者にはPCB特別措置法や廃棄物処理法にもとづいた届け出、適切な保管、そして処理する義務が生じます。つまり、0.5mg/kgを超える含有が確認された時点で管理対象機器となるのです。さらにPCB含有電気工作物は、濃度によってふたつの区分に分けられます。ひとつはPCB濃度が5,000mg/kgを超える高濃度PCB含有電気工作物、もうひとつは0.5mg/kgを超え、かつ5,000mg/kg以下の低濃度PCB含有電気工作物です。
この分類によって、処理の方法や扱いに違いが出てくるため、注意しなければなりません。PCBは低濃度だからといって安全というわけではなく、PCBは微量でも体内に蓄積しやすく、長期的な曝露によって健康被害を引き起こす可能性があります。そのため、濃度の大小にかかわらず、適切に保管し処分しなければなりません。
該当する可能性がある機器
高濃度PCB含有電気工作物に該当する可能性があるのは、経済産業省が告示で示している12種類の電気工作物です。具体的には、変圧器や電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器、そしてOFケーブルなどです。これらの機器に使われているPCB濃度が5,000mg/kgを超えていれば、高濃度PCB含有電気工作物として管理されます。一方、同じ12種類の機器であっても、PCB濃度が0.5mg/kgを超え、かつ5,000mg/kg以下であれば低濃度PCB含有電気工作物に分類されます。
処理期限が迫っている
PCB処理には明確な期限が設けられており、すでに2023年3月31日に設定されていた高濃度PCBの処理期限を経過しています。低濃度PCB含有廃棄物の最終期限は、2027年3月31日と目前に迫っているため、まだ対応していない事業者は迅速な行動が求められます。確認から届出、保管、そして処理施設への搬入まで一連の流れはある程度の時間がかかり煩雑ですが、法令にもとづいた手続きである以上避けられません。安全に留意して、専門家の協力を得ながら早めに対応を進めておきましょう。
キュービクル内のPCBを確認する方法
日本では2001年にPCB特別措置法が施行され、保有している事業者に対して厳格な管理と処分の義務が課せられました。そのため、事業者は自社の対象設備にPCBが含まれているかどうかを確認する責任があります。確認方法にはいくつかの手段がありますが、ここでは代表的な3つの方法を紹介します。製造年式
まず確認すべきは、製造年式です。キュービクル内で使用されている変圧器やコンデンサーなどは、一定の年代までPCBを使用して製造されていました。そのため、製造年を確認することで、PCB含有の可能性を推測することが可能です。またメーカーによっては、過去製品のうちPCBが使われている可能性のある機種を公表している場合もあります。そうした資料を照合することで、含有の可能性をより具体的に絞り込めます。
ただし、キュービクル内部を不用意に開けて調査するのは危険です。高圧電流が流れているため感電のリスクがあり、必ず電気工事の有資格者や専門業者に依頼することが大事です。
シリアルナンバー
次に確認すべきは、シリアルナンバーです。一般財団法人日本電気工業会が運営する「高濃度PCB機器 簡易検索ページ」を利用することで、保有する機器のPCB含有可能性を調べられます。調べる方法はかんたんです。サイト上で該当する機器の種類を選び、続いてメーカー名を入力すると、PCBが使われている可能性のあるシリアルナンバー一覧が表示されます。自社のキュービクルなどに搭載されている機器の番号と照合すれば、手間なく含有の有無を確認可能です。
成分分析
3つ目の方法は、専門業者による成分分析です。製造年式やシリアルナンバーでは判断できない場合、もっとも確実なのが、機器に含まれる成分を直接分析できる専門業者による検査です。検査機関に依頼し、分析した結果PCBが含まれていた場合、検査証明書が発行されます。この成分分析を実施するには、キュービクルの電源を一時的に停止し、トランスから検体用に絶縁油を抜き取る作業が必要です。稼働中の工場や施設では、業務に支障が出ないタイミングを調整する必要があるため、計画的に進めることが重要です。
キュービクルのPCB処分方法を知っておこう
事業者はPCB特別措置法にもとづき、保有するPCB含有機器を期限内に処分することが義務付けられています。処理の期限は決まっており、適切な手順で確実に処分を進めなければなりません。ここでは、届出、保管、最終的な処分までの流れを詳しく見ていきましょう。含有確認
処分の第一歩は、保有しているキュービクルにPCBが含まれているかどうかを確かめることです。とくに1953年から1972年に製造された変圧器やコンデンサーには、絶縁油にPCBが使用されている可能性が高いとされています。産業保安監督部への届出
PCB含有が判明した場合、電気事業法にもとづき産業保安監督部へ届け出る必要があります。機器がまだ使用中であっても同様で、期限内の廃止と処分を前提に届け出なければなりません。全国に10か所ある産業保安監督部は、経済産業省の公式サイトで住所と電話番号が確認できるので連絡しましょう。都道府県知事への届出
PCB廃棄物は、毎年6月末までに都道府県知事または政令市長へ処分や保管の状況を届け出なければなりません。また、PCB処理を一括して担うJESCOへの登録も必要です。必要な書類はJESCOのサイトで公開されているため、早めに準備しておくと安心です。PCB廃棄物の保管基準
処分までの間、PCBを含む機器は厳格に保管しなければなりません。保管場所は雨水の浸入や地下への浸透を防ぐ構造が求められ、施錠可能で関係者以外が立ち入れないことが条件です。さらに、保管場所にはPCB廃棄物保管場所である旨の表示を掲示し、事業者名や連絡先、処分予定時期などを明記する義務があります。さらに漏洩防止策として、防油堤や油受けの設置、吸収材の準備も欠かせません。加えて、定期的に点検を実施し、記録を残すことも求められており、管理には特定管理産業廃棄物責任者の選任が必要です。
JESCOへの搬入とマニフェスト
PCB廃棄物は、JESCOが管理する施設で処理されます。ただし、JESCOは運搬を担っていないため、PCBを運搬できる収集運搬業者と契約し、廃棄物を施設まで運んでもらいましょう。JESCOでは、処理の流れをトレースできるように産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストが発行されます。JESCOに搬入された後、2か月以内に処理完了を示すD票が返送されるので、契約書類とともに最低5年間保管しなければなりません。
低濃度PCB廃棄物の処分
低濃度PCBを含む廃棄物は、国や自治体に許可された民間処分場で処理可能です。都道府県知事または政令市長の許可を受けた業者と契約を締結、引き渡したあとでマニフェストが発行されます。費用軽減制度の活用
PCB廃棄物の処理には多額の費用がかかりますが、中小企業や個人事業主には負担を軽減する制度があります。法人は処理費用の70%、個人事業主は95%が補助される中小企業者等軽減制度です。申請後、JESCOの審査を経て契約が成立すると、軽減措置が適用されます。処理費用が大幅に抑えられるため、対象事業者は必ず活用したい制度です。